はじめに
2025年10月27日、日経平均株価が史上初の「5万円」を突破したその日、霞ヶ関キャピタル(3498)は前週末金曜日の引け後に発表した公募増資(PO)のニュースが投資家を直撃しました。
市場の祝賀ムードとは縁遠く、同社株が全銘柄中下落率トップとなる急落。SNSや掲示板では「せっかくの相場の勢いの恩恵が台無し」と非難の声も。
しかし、すべての増資が「悪」ではありません。今回は霞ヶ関キャピタルの事例をもとに、「良い増資と悪い増資」の違いを掘り下げていきます。
株をやるには圧倒的にmoomoo証券の活用・引っ越しがお奨め。まずは無料会員登録して情報収集し始めるところから!以下の関連記事もご参考ください!
👉関連記事 【投資家必見】moomoo証券が熱い!SOFIレバ2倍ETF&テンバガー候補7銘柄まとめ
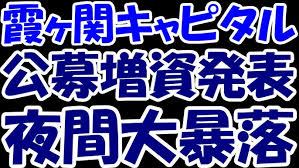
10/24発表の増資の中身
霞ヶ関キャピタルが発表したのは、約150億円規模の公募増資と第三者割当増資を組み合わせた資金調達。
調達資金の主な用途は次のとおりです:
- 物流施設・ホテル開発の新規プロジェクト投資
- REIT(不動産投資法人)との連携を見据えた資産循環モデルの拡大
- 有利子負債の返済による財務体質強化
つまり、単なる「赤字補填」や「運転資金確保」ではなく、成長を加速するための攻めの資金調達である点は注目に値します。
- 公募(新株)+第三者割当で発行される新株合計:4,691,500株。※内訳は公募4,000,000株+第三者割当691,500株。
- 発行前の発行済株式数(発表時点)は約19,811,258株。
- よって希薄化(既存株主の持分比率の減少)= 4,691,500 ÷ (19,811,258 + 4,691,500) ≒ 19.15%(約19.2%の持分薄化)。
- なお「発行される新株の規模を既存株式数に対する割合」で表すと 4,691,500 ÷ 19,811,258 ≒ 23.7%。(報道で“発行新株は現発行済み株式数の23.7%”と表現されているのはこの見方)
「23.7%」と「≈19.15%」の違い(ここ重要)
- 報道でよく見る 「新株は現発行済み株式数の23.7%」 は (新株数) ÷ (発行前の発行済株式数) の比率。増えた株数が“現状の株数に対してどれだけ大きいか”を示す。株探+1
- 投資家が気にする 「希薄化(自分の持分が何割減るか)」 は (新株数) ÷ (発行後の総株数) で見るのが正確。今回では 約19.15% がこれに相当する。つまり既存株主の持分は概ね約19%減る、と考える。StockWeather+1
資金規模と用途(要点)
- 調達の目安は報道ベースで約390〜524億円規模と報じられている(価格決定による幅あり)。発行価格は11/5〜11/10の「プライシング」で決定予定。
- 会社側の開示では、ホテル・物流・ヘルスケア事業の開発用地取得・開発資金・物件取得資金等に充当すると明記。借入ではなく株式での調達を選んだ理由も開示にある(中期計画実現のための安定した財務基盤構築)。
投資家として押さえるべきポイント
- 売出し610,000株は既存株主の持ち株売却なので“直接の希薄化”は生じない(ただし需給や流動性には影響)。
- **オーバーアロットメント(最大691,500株)**の扱いで市場に出回る株数は変動するため、最終的な希薄化はプライシングとオーバーアロット実行の有無で微増減する。
- 「発行前比で何%増えるか(23.7%)」と「発行後の持分比率が何%減るか(≈19.15%)」は用途と影響の議論で両方とも示されるが、投資家目線で重要なのは後者(自分の持分減少率)。
公募増資とは?
公募増資(Public Offering)とは、企業が新たに株式を発行して広く投資家から資金を集める方法です。
増資により企業は手元資金を潤沢にできますが、その一方で発行済み株式数が増えるため既存株主の持分が希薄化します。
つまり「資金を得る代わりに株主価値を一時的に薄める」構造です。
公募増資が株価に与える影響はケースバイケース。成長投資に使われるなら中長期的にはプラスとなり、逆に借金返済や赤字補填目的なら市場からは「防衛的」と受け止められ株価が急落しがちです。
今回の霞ヶ関キャピタルの増資のポジティブな点
霞ヶ関キャピタルは「悪い増資」ではなく、将来を見据えた布石と見ることもできます。
主なポジティブ要素を整理すると:
- 成長戦略と一貫している
→ 同社の強みである物流施設・ホテル開発に資金を投じる。これによりアセット循環型モデルをさらに拡大。 - REIT戦略とのシナジー強化
→ グループの不動産投資法人への物件供給能力が高まり、ストック型収益を拡大。 - 財務リスク軽減
→ 有利子負債の返済で信用力が向上。中長期的な資金調達コストも下がる見通し。
市場は短期的に“希薄化ショック”を嫌いますが、本質的には成長余力を高めるポジティブな増資と評価できます。
株価10000円に戻るのはいつごろか
今回の増資発表で株価は一時8,000円台前半まで下落。しかし、業績トレンド自体は崩れていません。
直近の決算では営業利益・純利益ともに過去最高を更新。ROEも20%超と依然高水準です。
過去の類似ケース(ヒューリック、野村不動産HDなど)を参考にすると、
「成長投資を目的とする公募増資後の株価回復には約3~6か月」かかるケースが多いです。
そのため霞ヶ関キャピタルも、来年の春頃(2026年3月〜4月)には1万円台回復が現実的なシナリオと考えられます。
まとめ
霞ヶ関キャピタルの増資は、市場の期待を裏切る形で短期的な株価下落を招きました。
しかしその中身を冷静に見れば、
- 成長戦略と整合的
- 財務健全化にも寄与
- REIT戦略との連携を強化
という**「良い増資」**に分類できます。
投資家が見るべきは「株が増えること」ではなく「何のために増やすのか」。
霞ヶ関キャピタルのケースは、まさに**“一時の痛みが将来の成長につながる”**典型例といえるでしょう。今後も同社の成長と株価に注目ですね。私は1枚も売りません。18000円までは!!

コメント